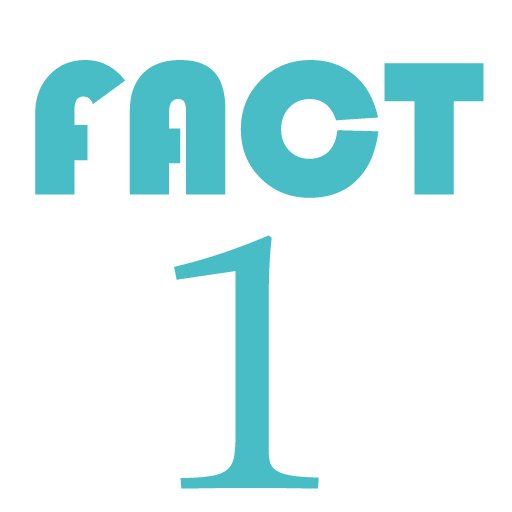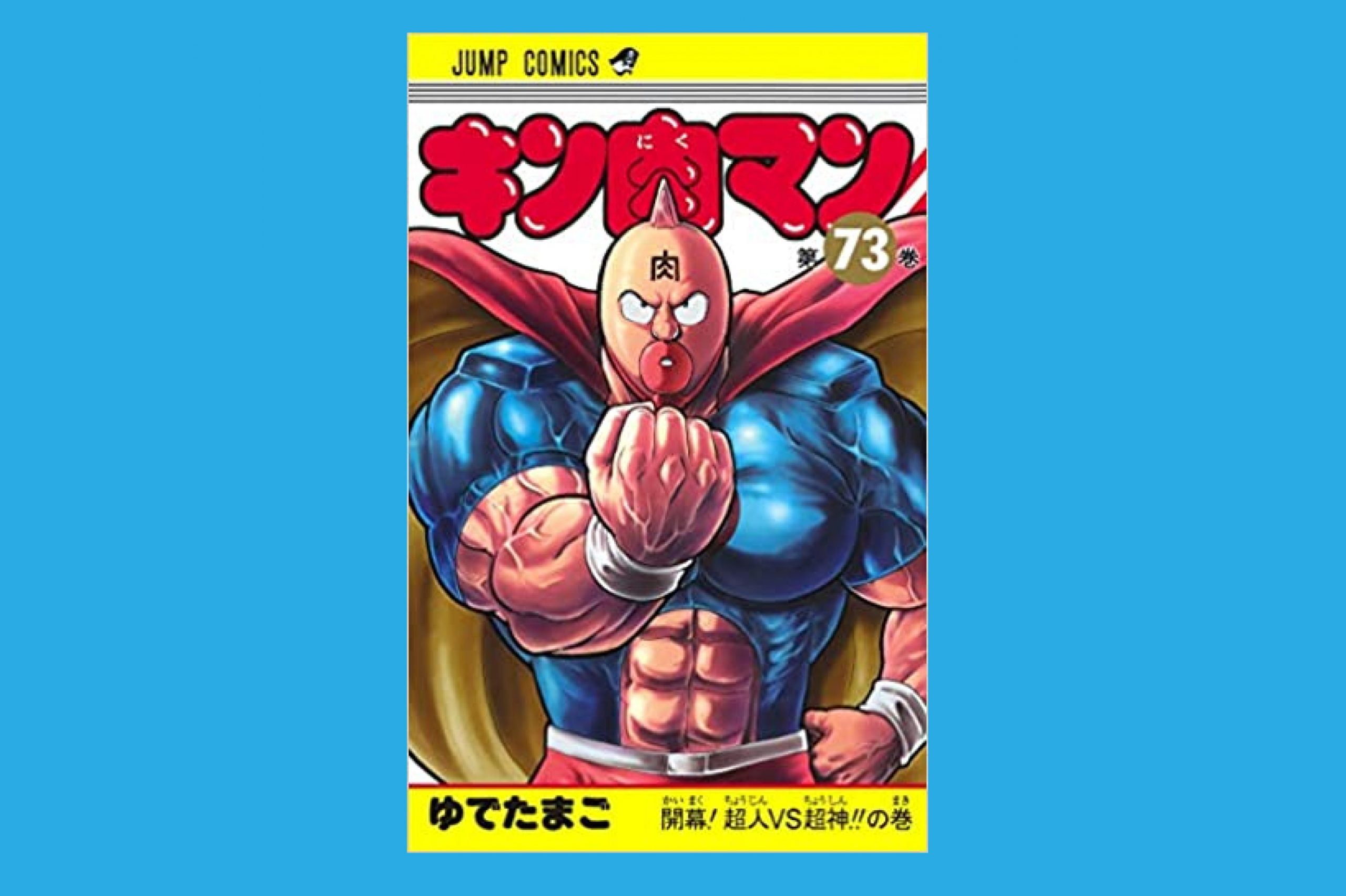『週刊少年ジャンプ』には昔から「バトルもの」と呼ばれる漫画が多く、特殊な能力や必殺技がその作品独自の理論によって生み出されています。
今でも多くのファンがいる『キン肉マン』にもそのような理論が登場しますが、中には子ども心に「?」と首をかしげてしまうようなものもありましたね。
今回は「子供ながらに首をかしげてしまった『キン肉マン』に出てくる理論」について聞いてみました。
100万×2×2×3=1,200万
「圧倒的に不利だったウォーズマンが、最後に使った戦法がすごかった。理論はあまりにも強引だったが、有無を言わせない説得力のようなものを感じた」
「ウォーズマンがバッファローマンのロングホーンをへし折ったシーンでの、ベアークローを両手に着け、2倍のジャンプと3倍の回転で1,200万パワーという理論。なにか引っ掛かるんだけど、展開があまりにも面白かったので『すげえー!』と言って受け入れていた」
『7人の悪魔超人編』での1場面。超人強度1,000万パワーを誇るバッファローマンに対し、パワーで劣るウォーズマンが一発逆転の秘策として繰り出したのが、「武器のベアークローを両手に装着(2倍)」「普段の倍の高さにジャンプ(2倍)」「普段の3倍の回転(3倍)」でのスクリュー・ドライバー。「100万×2×2×3=1,200万となり、バッファローマンの1,000万パワーを超える」という理論。少し無理がありますが技のシーンはとても格好よく、ウォーズマンの底力に感動した読者も多かったですね。
鎧の重みが移ると落下速度が増す
「奥の手だったロビン・スペシャルを、鎧を奪われて逆転されてしまうシーンを読んで『そんなのありか!』と声に出してしまった。でも、勢いのあるシーンで、なんとなく納得してしまった」
「ネプチューンマンがロビン・スペシャルを返すシーン。技の理屈を順序立てて解説しているが、鎧を取ると落下速度が逆転するというところがどうしても理解できなかった」
『夢の超人タッグ編』でロビンマスクが披露した新必殺技「ロビン・スペシャル」。「鋼鉄の鎧の重さによって相手よりも速く落下する」のがこの技の肝でした。対戦相手のネプチューンマンはロビンマスクの鎧を空中で奪って落下速度をアップさせ、「掟破りのロビン・スペシャル」を決めました。一般的に知られる「落体の法則」に矛盾していますが、ネプチューンマンの圧倒的な強さを見た読者は、物理法則のことよりもこれから戦うであろうキン肉マンの身を案じたものです。
汗で作った雨雲から塩水の雨
「モンゴルマンが汗を蒸発させて塩水の雨を降らせていた。子どものころは『モンゴルマンってすごい!』と納得してしまっていたが、よく考えたらいくら汗でできた雨雲だからって、塩分は含まれないのでは?」
「モンゴルマンは頭脳派ですごく強かったけど、汗で作った雨雲から塩水の雨が降るという理論には『そんなバカな』と思った」
『7人の悪魔超人編』で登場した、謎の超人モンゴルマン。キン肉マンとタッグを組んでのバッファローマン&スプリングマンとの戦いでは、大量の汗をかいて雨雲を発生させ、塩水の雨を降らせるという大技(?)を繰り出しました。しかし、例え汗を蒸発させても本当に蒸発するのは水分だけで、雨雲にも雨にも塩分は含まれないはずですよね。冷静になれば気が付きそうなものですが、このモンゴルマンの理論には、多くの読者が丸め込まれてしまいました。
6をひっくり返すと9になる
「『6をひっくり返すと9になる』という理論によるキン肉バスター破り。強引な気がしなくもないけど、見た目としてはその通りで説得力もある理論だと思う」
「キン肉バスターを返す時の『6をひっくり返すと9になる』というのはよくできた理論だと思った。そもそも数学で『6をひっくり返す』なんていうことが不自然だけどね」
『7人の悪魔超人編』のクライマックス、キン肉マン対バッファローマンの試合で、それまで絶対的な必殺技だったキン肉バスターが、バッファローマンによって破られてしまいました。「6をひっくり返すと9になる」とは、その際のバッファローマンのせりふです。単純にキン肉バスターを逆さまにするだけなのですが、数字の6と9を使った絶妙な言い回しに興奮した読者は多かったですね。
キン肉マンが地球!?
「プラネットマンが『地球はキン肉マン、キン肉マンに勝つことは地球を奪うこと』みたいなことを言っていた。バルカンという星の説明くらいまではまあよかったけど、キン肉マンが地球というのはちょっと強引だなと思った」
「プラネットマンの正体が惑星バルカンという設定は面白かったが、キン肉マンに勝てば地球を奪えるという理論にはびっくりした」
『黄金のマスク編』に登場したプラネットマンの正体は、地球の裏側に潜んでいた太陽系12番目の惑星「バルカン」でした。プラネットマンは地球を奪うのが目的で、その地球がキン肉マンであり、キン肉マンに勝つことが地球を奪うことだと宣言しました。あまりにもスケールが大きすぎて、ちょっと付いていけなかったという人もいましたね。
『キン肉マン』に登場する理論は、その場面を最初に読んでいるときは勢いに飲まれてしまってスルーしてしまうことも多いのですが、後で落ち着いて考えると「あれ?」ということがあります。それでも「キン肉マンだから仕方ない」と受け入れてしまう人が多いのは、それだけ作品が愛されているからでしょうね。
(松田ステンレス@dcp)